まだまだ暑い日々、ニンバス株とは?子どもに多い“のどの激痛”に注意
今年の秋は、猛暑が続く異例の気候の中で、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」の新たな変異株「ニンバス株(NB.1.8.1)」が流行しています。
特に子どもたちの間で「飲み込めないほどの強いのどの痛み」が目立っており、保護者の方々からのご相談も増えています。
今回は、ニンバス株の特徴や、家庭でできるケア、受診の目安についてご紹介します。
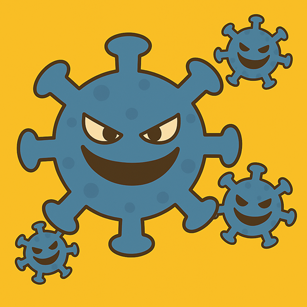
猛暑の秋、体調不良が増えています
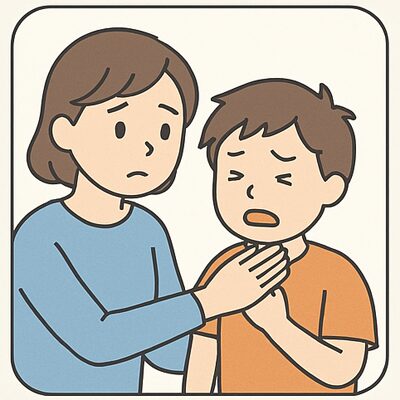
今年の9月は、例年にない残暑が続いています。各務原市でも連日30℃を超える真夏日が観測されており、暦の上では秋でも、体感はまだまだ夏のようです。こうした気温の乱れは、子どもたちの体調に大きな影響を与えます。
特に小さなお子さんは、体温調節機能が未熟なため、暑さによる疲労や脱水、睡眠不足などが重なり、体調を崩しやすくなります。保育園や学校が再開するこの時期は、生活リズムの変化も加わり、風邪のような症状が出ることも少なくありません。
保護者の方からは、「風邪かな?」「熱中症かも?」「もしかして新型コロナウイルス感染症(COVID-19)?」といった声が多く寄せられています。特に最近では、のどの激しい痛みを訴えるケースが増えており、従来の風邪とは異なる印象を受けることもあります。
こうした背景の中で注目されているのが、新型コロナウイルスの変異株「ニンバス株(NB.1.8.1)」です。次の章では、このニンバス株の特徴と、子どもに多く見られる症状について詳しくご紹介します。
ニンバス株の特徴とは?
2025年夏以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の新たな変異株「NB.1.8.1(通称:ニンバス株)」が国内外で広がりを見せています。オミクロン系統の一種でありながら、これまでの株とは異なる症状が報告されており、特に“のどの激しい痛み”が目立つのが特徴です。
最大の特徴は「のどの激痛」
ニンバス株では、急性咽頭炎のような強い痛みが初期症状として現れることが多く、「カミソリで切られたような痛み」「飲み込むのもつらい」といった表現が使われるほどです。
子どもたちはこの痛みをうまく言葉にできないため、食欲の低下や水分摂取量の減少、ぐったりした様子などから保護者が気づくケースが多くなっています。
その他の症状と風邪との違い
ニンバス株の症状は、一般的な風邪やインフルエンザと似ている部分もありますが、いくつかの違いがあります。
| 症状 | 風邪 | インフルエンザ | ニンバス株 |
| のどの痛み | 軽い〜中程度 | 中程度 | 非常に強い(嚥下困難) |
| 発熱 | 微熱〜高熱 | 高熱(急激) | 38℃前後が数日続く |
| 咳・鼻水 | あり | あり | アレルギー様の鼻水+乾いた咳 |
| 倦怠感 | 軽度 | 強い | 中程度(子どもはぐったり) |
| 味覚・嗅覚障害 | あり | まれ | ほぼなし |
このように、のどの痛みの強さと持続性が、ニンバス株を見分ける大きなポイントになります。特に小児では、症状の訴えが曖昧になりがちなので、保護者の「いつもと違う」と感じる直感が重要です。
子どもに多い症状と気づき方
ニンバス株(NB.1.8.1)による感染では、のどの強い痛みが特徴的ですが、子どもはその痛みをうまく言葉で伝えられないことが多くあります。特に幼児や低学年のお子さんの場合、「のどが痛い」とは言わずに、食べるのを嫌がったり、飲み物を口にしなくなったりすることで、異変に気づくケースが目立ちます。
飲み込みづらさ・食欲低下・水分不足
- 食事中に「痛い」と言う、または食べるのを途中でやめる
- 好きな飲み物でも口にしない、ストローを嫌がる
- 水分摂取量が減り、尿の回数が少なくなる
- 冷たいもの(ゼリー・アイス)だけを欲しがる
これらの様子が見られた場合、のどの痛みが強くなっている可能性があります。特に水分不足は脱水症状につながるため、注意が必要です。
観察ポイント:言葉にできない痛みを見逃さない
- 食事や水分の摂取状況
- 表情(しかめ面、口を押さえる、泣きやすい)
- 活気の有無(遊ばない、ぼーっとしている)
- 睡眠の質(夜中に起きる、寝つきが悪い)
保護者の「いつもと違う」という直感はとても大切です。医療機関では、こうした日常の変化を手がかりに診察を進めることが多いため、気づいたことをメモしておくのもおすすめです。
受診の目安とタイミング
以下のような症状が見られる場合は、早めの受診をご検討ください:
- 飲み物をほとんど口にしない/水分が取れない
- 高熱(38℃以上)が続く
- のどの痛みが強く、食事ができない
- ぐったりしている/反応が鈍い
- 呼吸が苦しそう/咳が止まらない
当院は、地域のかかりつけ医として、のどの痛みや発熱などの症状に対応しております。ご不安な場合は、まずはお気軽にご相談ください。
ご家庭でできるケアと予防策
ニンバス株(NB.1.8.1)による感染では、のどの強い痛みが主な症状として現れるため、家庭でのケアがとても重要です。特に小児の場合、症状の進行が早いこともあるため、早めの対応と予防が体調の回復につながります。
加湿・冷たい飲み物・やわらかい食事の工夫
- 室内の加湿は、のどの乾燥を防ぎ、痛みの緩和に役立ちます。加湿器がない場合は、濡れタオルを干すだけでも効果があります。
- 冷たい飲み物(麦茶・スポーツドリンク・ゼリー飲料など)は、のどの炎症を和らげながら水分補給にもなります。
- 食事は、刺激の少ないやわらかいものを中心に。おかゆ・うどん・ヨーグルト・ゼリーなどが食べやすく、栄養も摂りやすいです。

水分補給は“のどの痛み”と“熱中症”の両方に効く
猛暑が続く今年の秋は、のどの痛みと熱中症の症状が重なりやすい時期です。ニンバス株による感染では、のどの痛みが強くなることで水分摂取が難しくなり、結果として脱水症状や熱中症のリスクが高まります。
子どもは「喉が渇いた」と言う前にすでに脱水が始まっていることもあるため、こまめな水分補給が不可欠です。以下のような工夫が効果的です。
- 1時間おきに声かけをして飲ませる(遊びや勉強に夢中になっている時ほど注意)
- 麦茶・水・スポーツドリンク・経口補水液など、状況に応じた飲み物を選ぶ
- 冷たいゼリー飲料やアイスなど、のどの痛みが強い時でも飲みやすいものを用意
- 塩分補給も忘れずに:スープ・梅干し・塩分タブレットなどを食事に取り入れる
また、室内の温度管理や服装の工夫も熱中症予防には重要です。エアコンや扇風機を適切に使い、湿度を60%以下に保つことで、のどの乾燥も防げます。
手洗い・マスク・換気などの基本対策
- 外出後や食事前の手洗いは、感染予防の基本です。石けんを使って20秒以上洗うようにしましょう。
- マスクの着用は、のどの保湿にもつながります。特に人混みに行く際は着用をおすすめします。
- 室内ではこまめな換気を。暑さが残る時期でも、短時間でも空気を入れ替えることでウイルスの滞留を防げます。
睡眠と栄養で免疫力を支える
- 子どもは睡眠不足になると免疫力が低下し、感染しやすくなります。早寝・早起きの生活リズムを整えることが大切です。
- 食事では、ビタミンC・たんぱく質・鉄分などを意識して摂ることで、体の回復力と抵抗力を高めることができます。
地域の皆さまへ
各務原リハビリテーション病院は「病院」という名称ではありますが、地域の皆さまの“かかりつけ医”として、日常的な体調不良や感染症の診療に対応しております。のどの痛みや発熱、咳などの症状についても、これまで多くのお子さんを診てきた経験をもとに、丁寧に診察・対応させていただいております。
特に今年のように、猛暑と感染症が重なる時期は、保護者の方が「受診すべきかどうか」で迷われることも多いかと思います。そんな時こそ、「ちょっと気になる」段階でのご相談が、重症化の予防につながります。
また、診察の際には、保護者の方が気づいた症状や変化(食欲・水分摂取・元気度など)をお伝えいただけると、より的確な判断がしやすくなります。「いつもと違うかも」と感じたら、遠慮なくご相談ください。
当院では、初めての方でもご予約なしで診療を受けていただけます。ただし、事前にお電話やオンライン予約をご利用いただくと、よりスムーズにご案内できます。
また、発熱や咳、のどの痛みなどの症状がある場合は、事前にお電話でのご相談やオンライン予約をお願いしております。お子さまや他の患者さまが安心してご利用いただけるよう、皆さまのご協力をお願い申し上げます。 地域の皆さまが安心して秋を過ごせるよう、今後もわかりやすく、実践的な情報を発信してまいります。
関連記事
発熱外来のご案内(2025.01.24)
子どもの発熱、熱中症と感染症の見分け方と対策(2025.06.18)
子どもの隠れ脱水とは?症状チェックと家庭でできる対策まとめ(2025.07.10)
梅雨に増える子どもの感染症、気づくサイン(2025.06.26)
冷たいものの摂りすぎに注意!世代別に見る体への影響と対策(2025.07.15)
監修:各務原リハビリテーション病院長 磯野 倫夫
執筆:医療法人社団 誠道会 広報担当


